📘【第14話】
サブタイトル:朝メシとオバチャン
「お兄ちゃん、今座ったばっかやろ? 味噌汁とごはんもう出るけんね!」
カウンターに腰を下ろした瞬間、鬼丸の目の前に白ごはんと味噌汁が並んだ。まだメニューも見ていない。というか、そもそもメニューらしきものが見当たらない。
「……すげえな、こりゃ戦場やな。注文が飛び交って、配膳も秒で決まっとる。厨房がまるで前線の指揮所みたいや」 思わず小声でつぶやく。
時刻は朝の5時半。外はまだ肌寒く、眠気も残る時間帯だが、店内はすでに活気に満ちていた。カウンターの奥のテーブルでは、地元の土建屋風の男たちが煙草片手に朝から賑やかに談笑している。テレビでは天気予報が流れ、味噌汁の湯気とともに店内に漂うのは、どこか懐かしい煮干しと醤油の匂い。それは、子どもの頃に祖母の家で食べた朝ごはんの匂いに似ていた。まだ布団の中にいた自分を起こすように、台所から漂ってきた湯気とだしの香り──その記憶がふと蘇り、鬼丸はほんの少しだけ目を細めた。
「はいはい、焼き鯖に卵焼き、あと納豆つけとったよね?」 「いや、俺初めてなんですけど」 「大丈夫大丈夫、うち初めての人でも“うちの常連”にしとるけん!」
鬼丸は苦笑いを浮かべた。ここまで押しが強いと、もはや感心すら覚える。
「ごはん大盛りでいいよね?」 「いや、普通で……」 「はい、大盛り〜!」
エプロン姿のオバチャンが、笑顔で返す。年齢は60代後半、背は小さいが声はでかい。元気と勢いでこの店を回しているのは間違いない。
目の前には、気がつけば焼き鯖、卵焼き、納豆、小鉢、漬物、そして味噌汁がズラリと並んでいた。
「……これぞ、朝メシ界のフル装備やな。もう、準備万端で迎え撃たれる感じや」
思わず口元がゆるむ。箸を取ると、ふわっと香ばしい鯖の匂いが鼻をくすぐった。 「……うまそ」
ひと口目。脂ののった鯖に、ほんのり甘い卵焼き。口の中でじんわり広がる味に、思わず目を閉じた。
「お兄ちゃん、トラックやろ?」 「あ、はい、よくわかりましたね」 「だいたいわかるっちゃん、顔が“夜と戦ってきた顔”しとるけん」
カウンター越しのオバチャンの目が、いたずらっぽく光る。
「いつもどこ走りよると?」 「九州から関西、たまに東京もですね」 「そりゃ遠いね〜。そげん走っとったら腰にくるやろ。運転中眠くなったら、うちの味噌汁思い出してよ。絶対目ぇ覚めるけん!」
土建屋の兄ちゃんたちが「それは言いすぎやろ!」とツッコミを入れ、店内に笑い声が広がる。
箸を進めながら、鬼丸も思わず吹き出してしまった。体の奥に染み込んでいた緊張が、少しずつほどけていくのがわかる。
「うちはね、常連も初めての人も、朝から元気にして帰ってもらうのが仕事やけん」 オバチャンがポットを持って再び現れ、お茶を注いでくれた。
「たまにはこういう朝も、ええね……」 鬼丸は心の中でつぶやいた。
食べ終わる頃には、肩の力がすっかり抜けていた。
「お代、いくらですか?」 「今日はサービスよ。初めて来た人は“うちの家族”やけん」
「いやいや、それはさすがに……」 「次来たとき2倍払ってくれたらよかよ」
オバチャンの笑顔に押し切られ、鬼丸は頭を下げて店を出た。
外の空気は少しだけ暖かくなっていた。
朝日が低い角度から町を照らし、トラックのフロントガラスが光を受けて静かに輝いていた。
「さーて、次はどこの荷物が俺を待っとるかね。……ま、腹も満たされたし、どこでもかかってこいや」
缶コーヒーのプルタブを引きながら、鬼丸はにやりと笑った。
車のドアを開けると、座席にはさっきオバチャンがこっそり忍ばせた“おにぎり2個入り”のビニール袋。
「……どこまでサービス精神旺盛なんや。ほんま、こっちの心まで詰め込んでくれとるみたいやな」
鬼丸は苦笑いしながらエンジンをかけた。
エンジン音が響く中、町の風景が少しずつ遠ざかっていく。
その後ろに、あの店の暖簾が、静かに揺れていた。

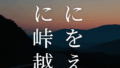

コメント