娘編 第5章】
サブタイトル:朝の白衣と夜の鞭
白衣を羽織ると、背筋が自然と伸びた。無意識に口元を引き締め、ナースステーションの明かりの下へ向かう。 制服のポケットには、新しいメモ帳とペン、小さな体温計が入っている。メモ帳の端には癖のある自分の字でびっしりと申し送り事項が記され、何度も読み返した跡があった。ペンは決まってジェットストリームの0.5ミリ。細かく書けることとインクの滑らかさが気に入って、何本もリピートしている。体温計のキャップには、小さな猫のシール。誰に見せるわけでもないけれど、夜の自分とは異なる、柔らかな部分を思い出すための小さな印だった。
──ここでは“あかり”でいなければならない。
ナースコール、咳、プリンターの機械音。 この空間ではそれらがすべて「日常」であり、「責任」でもある。 電子カルテの画面がまぶしく目にしみる。 朝のミーティング、患者のバイタルチェック、点滴の確認。 手際よく仕事をこなす姿に、同僚たちは一目置き、後輩からも頼られることが増えてきた。つい先日、新人の佐藤が点滴ラインをうまく取れず焦っていたとき、あかりはさりげなく声をかけ、静かに処置を代わった。処置後、佐藤が「先輩、どうしてそんなに落ち着いていられるんですか」と漏らしたとき、あかりは少し微笑んで「慣れよ」とだけ返した。その言葉の奥には、昼と夜を通り抜けてきた時間が確かにあった。
けれど、誰も知らない。昨夜、ヒロという男の前で“カレン”として立っていたことを。
カウンターの奥で見た彼の目は、確かに揺れていた。壊れそうな硝子のように、痛みと後悔で曇っていた。その目を見た瞬間、カレンとしての“支配”ではなく、あかりとしての“理解”が先に動いた気がした。あれほど自分を押し殺して生きてきた男が、壊れるほどの言葉をどれほど抱えていたのか。
それが──少しだけ怖かった。
それは目の前の誰かが崩れていくことへの恐れではない。 自分の中にも同じような思いや言葉が潜んでいて、ヒロの涙がそれを呼び起こしそうになったこと。 “支配”する側でいるはずの自分が、“共鳴”してしまうことへの戸惑い。 夜の“カレン”が持つべき役割を逸脱してしまうことへの、微かな危機感だった。
感情を持ち込んではいけない。線引きが必要だ。 昼の私は命を支える者、夜の私は心を解放させる者。 その境界が曖昧になれば、私は立っていられなくなる。 それが、あの人──母との約束だった。
──「二つの顔を使い分けなさい。どちらもあなたよ」
母の声が、静かに頭の中で響く。 思えば、学生時代に一度だけ聞いたことがある。 「あなたの父親に、最初に“弱さ”を見せたとき、すべてが終わった気がした」と、ぽつりと漏らした母の言葉。 その一言が、あかりの心に今も残っている。 あの人もまた、何かを抱えていたのだろう。
ロッカーの奥に見える黒いドレスの端が、ふと目に入る。 あの夜にまとった衣装。それは単なる衣ではない。 自分が“カレン”になるための鍵であり、殻であり、そして鎧だった。
白衣のポケットに指を差し込むと、そこには昨夜ヒロに渡した洋書と同じシリーズの小冊子が入っていた。 それは偶然ではなかった。何かを期待していた自分の証。
彼は、読むだろうか。 そして、自分の罪をどう抱え、どう乗り越えていくのだろう。 私は、それを見届ける資格があるのだろうか。
私は……私は、どうなのだろう。
病室の窓の外に目をやる。 薄曇りの空に、柔らかな朝の光が差し込んでいた。 通学中の子どもたちの列、遠くに響くゴミ収集車のエンジン音。 この街の朝は、何事もなかったかのように、静かに始まっていく。
夜の鞭よりも、朝の光のほうが冷たいと感じる瞬間がある。 夜には許される矛盾や歪みが、朝の光の下では、あまりにもくっきりと浮かび上がってしまうからだ。 けれどそれは、私がまだ“カレン”でいようとしている証なのかもしれない。
私は今日も、“あかり”として病院を歩き出す。 白く、静かに、けれど確かに。
そして、その歩みの中で、“あかり”と“カレン”の境界線を、少しずつ問い直している自分に気づいている。 夜の自分が見た涙に心が揺れ、昼の自分がその余韻を引きずっている。 ほんの小さなこと──後輩にかける言葉の温度、患者の手を握る指の圧、白衣の中で一瞬だけ立ち止まるその間合い。 そのひとつひとつに、どちらの自分の影が混ざっているのかを、確かめるようにしている。


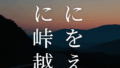
コメント