📘【第13話】
サブタイトル:静かに峠を越えて
峠を越えたのは、まだ空が白みきる少し手前だった。山の向こうがかすかに明るくなってきているのが、バックミラー越しに見える。
エンジンの音だけが、一定のリズムで車内に響いていた。鬼丸はゆっくりとブレーキを踏みながら、ハンドルを切り、下り坂へと滑り込んでいく。
さっきまで助手席に座っていた、あの女のことが頭から離れなかった。 肩までの黒髪、グレーのフード付きコート。言葉少なで、笑うでもなく、睨むでもなく──なのに、不思議とこちらの内側に踏み込んでくるような眼差しをしていた。見た目は平凡なはずなのに、どこか現実から浮いているような、浮世離れした雰囲気があった。
名前も名乗らず、行き先も曖昧。会話のどこかが噛み合わない。それなのに、最後に放たれたひと言が、鬼丸の胸に深く刺さった。
「あんた、ずっと“言葉”で迷ってきた人やろ」
否定できなかった。その言葉が、鬼丸の中で何度も何度も反響していた。思い返すたびに、その通りだとしか思えなかった。
鬼丸はラジオに伸ばした手を、無意識にスイッチへ。切った瞬間、車内に静寂が流れ込む。自分の呼吸の音が、やけに大きく聞こえた。
ふと助手席に目をやると、シートの上に一本の髪の毛が落ちていた。まっすぐで黒く、まだぬくもりが残っていそうな細い髪。
「……まさか。いや、まさかな。幽霊とか……さすがにそれは年のせいやろ」
鬼丸は自分で苦笑いしながら、指先でそれを摘み、窓を少しだけ開けて放った。 夜明け前の冷たい風が、指に触れて、じんとしみる。その感覚は、まるで忘れかけていた誰かの手にそっと触れられたような──そんな懐かしさと、わずかな不安が混ざっていた。
髪の毛は、ふわりと浮かんで、すぐに闇の中に消えていった。
女が降りた集落を、鬼丸はもう一度思い返す。コンビニも、自販機も、灯りすらない。ただ錆びたバス停と、屋根の崩れた廃屋のような家が一軒、ぽつんと立っているだけだった。
「廃屋かと思ったら……洗濯物、干してあったもんな。現役かい。たまげた」
小さく漏らした言葉に、もちろん返事はない。それでも、その静けさが心地よく感じられる。 不思議と、寂しさはなかった。
──言葉で迷ってきた。
確かにそうかもしれん、と鬼丸は思う。 あのとき何も言わなかったことで終わった関係、言わなければよかったことで壊れた時間。 たとえば、まだ若かったころ。娘の進路をめぐって激しくぶつかった日のことが頭をよぎる。感情に任せて言い過ぎた。あのひと言がなければ、あんなに長く口をきかないまま別れることはなかったかもしれない。
そんな記憶のひとつひとつが、今でも胸の奥に棘のように刺さったままだ。
もう一度やり直すことはできない──それはよくわかっている。 けれど、これから出会う誰かには、せめて間違った言葉ではなく、ちゃんと向き合う言葉を選びたい。
そう思えるようになっただけでも、峠の向こうに進んだ意味があったのかもしれない。
前方、山あいの町の光がぼんやりと滲んで見えてきた。オレンジと白が混ざり合ったやさしい明かり。その光は、どこか懐かしく、過去と重なる匂いを帯びていた。
それが現実の風景なのか、それとも記憶の中の残像なのか、鬼丸には判然としなかった。
昔、まだ妻と暮らしていた頃。夏の帰省の途中に立ち寄った山間の町。 その静けさ、涼しさ、どこか寂しげな風景── 娘がまだ幼くて、妻は今より少しだけ笑っていた。
今見えている光景と、その記憶が、どこかで静かに重なっていた。
「……そろそろ、次のページをめくらにゃいかんやろ」
口にした自分の声に、少しだけ重みを感じた。 けれど、それが嫌ではなかった。むしろ、どこかでずっと待っていた言葉のように思えた。
鬼丸はアクセルを踏み直す。トラックが少しだけ揺れ、また静かに動き出す。
窓の外、空は確かに明るくなり始めていた。 夜の終わりと、朝の始まり──その狭間を、鬼丸は静かに越えていく。
ゆっくりと、しかし確かに。
見えてきたあの町で、何かが少しだけ変わるかもしれない──そんな予感を胸に、ハンドルを握り直した。
「……その前に、朝メシ食えるとこ見つけんと腹が鳴るばい」


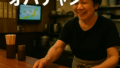
コメント